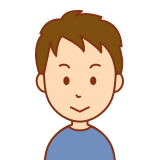
行政書士についてネットで見ると、簡単という意見や難しいという意見があって実際どうなのか気になります。
こんな疑問を持つ方はいませんか?
この記事では行政書士試験が難しいと言われている理由を具体的に解説していきます。
この記事を書いている僕は行政書士に独学で合格して実際の難易度も分かることが信頼性の担保になると思います。
それでは早速見ていきましょう。
【結論】行政書士はゼロから目指すなら圧倒的に難しい

まず行政書士が簡単か難しいのかについての僕の見解はというと、「圧倒的に難しい」です。
もちろん人によって前知識や学歴、バックボーンは違うので一概には言えません。
元法学部の人は相当有利だし、司法試験受験生にとっては行政書士なんて朝飯前レベルに感じるかもしれないです。
僕が言っているのは、これまであまり勉強してこなかった人、法律系の資格も持っていなくてゼロからスタートする人にとっての難易度です。
数年前の僕が行政書士試験の勉強をスタートする時も完全にゼロからスタートしました。
法学部でもないし他の資格も持っていない、法律関係の本なんて一冊も読んだことのない状態です。
そこから合格までの道のりは決して楽とは言えないものでした。
と言うか、めちゃくちゃしんどかったです(笑)
だから僕は行政書士が簡単だなんて1ミリも思っていません。
そんな経験を通して特に行政書士が難しいと感じる理由を次の項目から解説していきます。
これから行政書士に挑戦する人は覚悟してください(笑)
▼あわせて読みたい記事はこちら▼
巷で行政書士が難しいと言われる理由4選

行政書士試験が難しいと言われる理由で考えられることを4つのポイントにまとめてみました。
これを読めば行政書士の難しさが簡単に分かります。
膨大な試験範囲
行政書士の試験範囲を一通り終えた僕は絶句しました。
「えっこんな範囲広いの?!一通りやるのにこんだけ時間かかるとは思わなかった・・・」
行政書士試験は法律科目と一般知識科目から成り、
- 憲法
- 民法
- 行政法
- 会社法
- 個人情報保護法
- 一般知識
などの多くの科目があります。
これらは1科目やるだけでも相当のボリュームがあり、全部をやろうと思っては時間がいくらあっても足りません。
やってもやっても終わらなくて、時間が経てば経つほど覚えた内容を忘れていく恐怖を感じたことはありますか?(笑)
こういう理由なので、通信講座で効率良く学習したり、独学の場合でも学習の計画をきちんと立てて自己管理していく必要があります。
厄介な記述式
行政書士試験は基本はマークシートの試験なのですが、一部記述式で答えないといけない問題があります。
全部で300点満点中、記述式部分が60点あり、結構な割合となります。
マークシートは勘で答えてたまたま正解することもありますが、記述式だとそうはいきません。
実力がモロに出るので、本当にしっかり理解していく必要があるのです。
「記述式でもう少し得点できたら合格だったのに・・・」と枕をぬらす受験生は毎年相当多いでしょう。
足切りが恐い一般知識
一部の受験生に恐れられているのが一般知識の足切りです。
いくら法律科目で得点できても最低限一般知識の足切りラインを超えていないと不合格になってしまいます。
その足切りラインは40%なのですが、ここで引っ掛かって法律科目は余裕で合格点なのに落ちてしまう人も結構います。
一般知識の問題は、
- 政治
- 経済
- 社会
- 個人情報保護法
- 文章理解
などで範囲が広く、何が出るか分かりにくいので対策しにくい問題です。
高校の時に「政治・経済」や「現代社会」が好きだった人とか、センター試験の勉強をしたことがある人は多少有利になるはずです。
ちなみに僕は政治経済と現代社会が得意科目だったので一般知識の足切りは余裕でクリアしました(笑)
低い合格率
そもそも行政書士は合格率が10%前後と非常に低いので、そう簡単に受かるわけがありません。
10人受けて9人が落ちる試験をたいして勉強しないで適当に受けて合格はしないでしょう。
何故か行政書士は簡単だと思っている人は合格率の数字を知っているのでしょうか。
何百時間と勉強しても落ちる人はいるし、数年がかりで合格する人だっている試験なのです。
行政書士で一番難しい科目は?
どれも難しいです(笑)
あえて選ぶなら、民法や会社法は苦手で難しく感じました。
聞くところによると僕と同じように民法を苦手とする受験生は多いようです。
民法は条文数が多すぎて、一通り勉強するだけでもかなり疲れますからね。
会社法に至っては量は多いし難しいし、配点的に低いしで本当に困りものです(笑)
ただ、合格するためにはなるべく捨て科目を作るべきではないので、難しい科目や苦手な科目でも根気強く勉強して得点できるようにしておく必要はあります。
苦手な科目の勉強はモチベーションが上がりにくく、なかなか苦痛だったのが印象に残っていますね。
行政書士に合格するのに必要な勉強時間は?
行政書士に合格するためには一般的に500~1000時間ほど勉強が必要と言われています。
僕は800時間超勉強してなんとかギリギリで受かりました。
多分要領の良い人なら500~600時間で受かるかもしれないし、要領の悪い人や運の悪い人は1000時間やっても受からないと思います。
感覚としては最初の200時間くらいまではサッパリ意味が分からなかったです。
で、300~500時間くらいでちょっとずつ問題が解けるようになって、500時間超えたあたりから実力が伸びていった感覚でしょうか。(適当ですよ)
これから勉強を始める人に一つだけ伝えたいのは、「最初は意味不明で当たり前だからそこで諦めないでくださいね」ということです。
行政書士より簡単なおすすめの法律資格は?
資格勉強をしたことが無い人がいきなり行政書士は少しハードルが高いかもしれません。
そこで行政書士を受ける前に挑戦するのに丁度いい法律資格を紹介します。
ビジネス実務法務検定
難易度的にもオススメですが、それ以上に学べる内容が素晴らしいビジネス実務法務検定。
社会人なら知っておいて損はないビジネスに関する法律知識がポイントを絞って学べます。
3級ならとても簡単なので、忙しい社会人でも大丈夫。
多分スキマ時間に勉強するだけでも受かるんじゃないでしょうかね。
スタディング ビジネス実務法務検定講座 ![]() という通信講座ではスマホやタブレットでスキマ時間学習が出来るので便利です。
という通信講座ではスマホやタブレットでスキマ時間学習が出来るので便利です。
宅建
宅建は合格率が15%程度で、必要な勉強時間が200~300時間と行政書士の取っ掛かりに非常におすすめな資格です。
宅建でも民法を学べるので、行政書士受験の無駄にならないことも良いですね。
法律の勉強にも向き不向きがあるので、いきなり行政書士に行くよりも、宅建で様子を見てからがベター。
宅建→行政書士と進んで法律の勉強が好きだと分かったらさらに上の司法書士とかを目指す人もいますよ。
ちなみに宅建を学習するならクレアール ![]() という老舗の通信講座が評判が良いです。
という老舗の通信講座が評判が良いです。
興味があれば無料の資料請求をしてみてはいかがでしょうか?
まとめ
いかがでしょうか?
行政書士試験が難しいと言われる理由を4つのポイントで解説しました。
最後に復習して終わりましょう。
- 試験範囲が膨大
- 記述式が厄介
- 一般知識の足切りがある
- 合格率が10%程度と低い
以上になります。
一部で言われている行政書士は簡単だという意見を鵜呑みにしてろくに勉強しないで玉砕するような事はないようにしましょう。
難しいとは言いましたが、凡人でも努力すれば受かるレベルだとは思うので、過度に恐れえる必要はありません。
働きながらでも、独学でも行政書士に受かっている人はたくさんいます。
では、ご精読ありがとうございました!
▼あわせて読みたい記事はこちら▼






