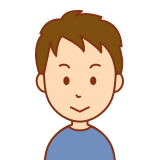
行政書士試験では「一般知識」の科目で足切りがあると聞きました。何か対策はありますか?
こんな疑問を持つ方はいませんか?
この記事では行政書士試験の中でも一般知識の科目にスポットライトを当て、どのような対策が効果的かを解説していきます。
ちなみに僕は試験科目の中でも一般知識は比較的得意な方でしたので、参考になる部分もあるかと思います。
ぜひ最後まで読んでみてください!
▼早く一般知識科目の過去問集を見たい方はこちら▼
行政書士試験の一般知識とは?
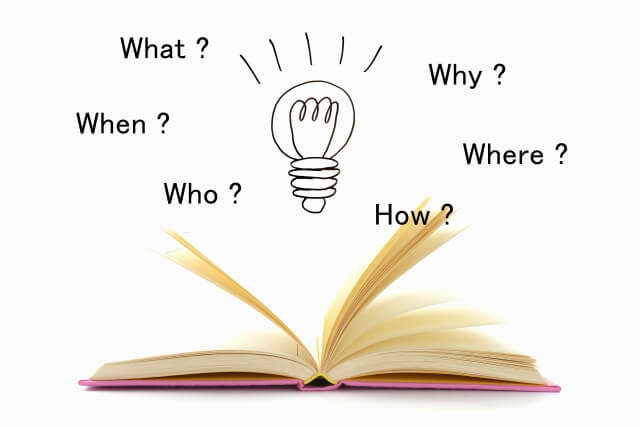
行政書士試験には法令科目だけでなく一般知識の科目として、
- 政治・経済・社会
- 個人情報保護
- 文章理解
の問題が出題されます。
それぞれ政治経済社会が7問、個人情報保護が4問、文章理解が3問ほどの割合で出題され、この中から最低4割は得点できないと「足切り」となり、例え法律科目が満点でも不合格となってしまいます。
毎年多くの受験生がこの「足切り」で涙を呑んでおり、対策をすることは必須となっています。
計14問の一般知識の問題の中から足切りを回避するために6問以上正解するためにやるべきことを以下で解説していきます。
行政書士の一般知識って難しい?
一般知識を苦手としたり難しいと感じる受験生は多いようです。
その理由の一つとして「どんな問題が出るか分からない恐さ」というものがあると思います。
政治経済社会の科目はとにかく範囲が広いので、出そうな問題を事前に全て勉強しておくなんて不可能です。
どれだけ勉強しても不安が付きまとい、自分が全く知らない知識を問われたらお手上げというプレッシャーがあります。
もう一つの理由として、「どこまで踏み込んで勉強するべきなのか分からない」ということがあります。
行政書士は言うまでもなく法律の試験なので、法律の勉強を中心にするべきです。
それなのに300点満点中たった54点しか配点のない一般知識に足切りラインが設けられ、勉強せざるとえなくなります。
仮に一般知識にかなりの割合の時間をかけてしまうと、必然的に法令科目が手薄になり、不合格という結果に近づいてしまうかもしれません。
ここら辺の塩梅がなかなかに難しいのです。
行政書士の一般知識のおすすめ勉強法

一番最初にやるべきことは「過去問10年分」です。
これをすることで問題に慣れ、今後の試験対策にもなるでしょう。
- どんなことが問われているか?
- 問題の切り口はどうか?
- 実際に解いてみて、手応えはどうか?
- 自分が苦手とするジャンルはあるか?
これらのことに意識して過去問に取り組みましょう!
過去問学習がだいたい終了したら次は個別の分野の勉強に入ります。
政治・経済・社会は新聞や公務員試験の速攻の時事を使う
14問中7問が出題される政治・経済・社会は学生の時の社会科の「現代社会」や「政治・経済」のような問題が出題されます。
社会科の授業が好きだった人やセンター試験の社会の勉強をしていた方などは有利になるでしょう。
そうではない人も対策法を書いておくので大丈夫です。
- 新聞を読む
- 公務員試験用の「速攻の時事」を使う
この2つが一般知識対策として有効だと思います、
例えば1日15分だけでも良いので、新聞をコツコツ読んでみてください。
政治・経済・社会の科目は毎日の積み上げ学習が有効。
世の中のニュースに興味を持ち、貪欲に知識を得ていきましょう。
新聞を活用すると自分が興味のあるジャンルだけでなく、普段は見向きもしないようなニュースが強制的に頭に入ってくるので、わりとおすすめです。
そして新聞を読む時間がないという方には公務員試験で大人気の「速攻の時事」というシリーズが良いです。
この参考書は政治・経済・社会などに関して、文字通り「速攻」で、コンパクトに要点を学習できる優れた参考書です。
個人情報保護法は過去問と条文読み込みがオススメ
個人情報保護の分野は行政書士の一般知識の中でもわりと得点しやすい分野です。
ここでしっかり点を稼いでいけるように確実に実力を付けていきましょう。
個人情報保護法の分野では過去問を何度も解いて、条文を読み込むというオーソドックスな勉強法がオススメです。
行政書士になった後でも知っておいて損はない知識が学べるので、時間の許す限り条文を確認しましょう!
文章理解はセンター試験の問題を解いたり普段から本を読む
文章理解の問題は多少長い文章が厄介ですが、問題自体はそこまで難しくありません。
長文にどれだけ慣れているかが鍵なので、普段から訓練しておくことが重要です。
長い文章を素早く理解できるように以下のような勉強をしてみてください。
- センター試験の現代文を解いてみる
- 普段から小説や本を読む
- 1日1題やってみる
残念ながら一朝一夕で文章理解の力は付きません。
逆に1日1題でもコツコツ継続すれば、段々と問題が解けるようになるはずです。
要は「普段から文章に慣れていきましょう」ということです。
行政書士の一般知識科目で足切りされないために

一般知識は足切りラインが40%に設定されています。
全部で14問あり、その中から6問は死守しなければ即アウトとなります。
そのためには各分野で目標を立てることがオススメです。
例えば、
- 政治・経済・社会は7問中2問が目標
- 個人情報保護は4問中2問が目標
- 文章理解は3問中2問が目標
これくらいが良いのかなと思います。
理想を言えば個人情報保護と文章理解でそれぞれ3問もぎ取り、政治・経済・社会で大失敗してもなんとか足切りはクリアできるくらいになれたら満点です。
しっかり勉強して望めば個人情報保護で2~3問は取れると思いますし、文章理解の問題も落ち着いて読めたら3問正解も見えてくるでしょう。
文章理解は焦ったらミスるので試験終了直前に取り組むのではなく、早い段階でやっておくのも良いと思います。
行政書士の一般知識はいつから勉強を始める?
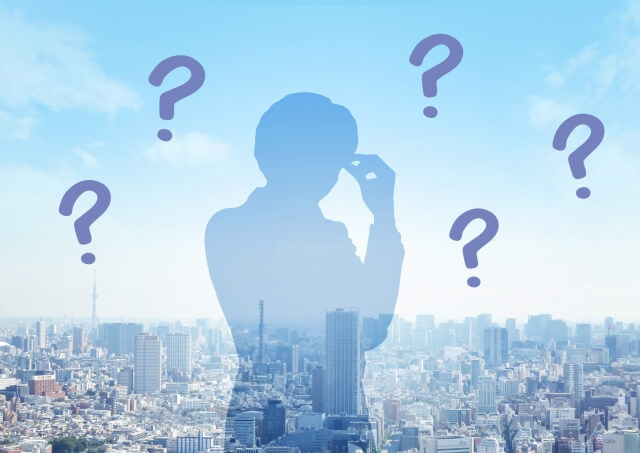
一般知識をいつから勉強するかはなかなか迷うところだと思います。
いきなり初期から始めてコツコツやるのも良いですし、試験が近づいてきて一気に詰め込むのも戦略としてアリかもしれません。
人それぞれになりますが、個人的には「試験半年くらい前から」が目安かなと思います。
やはり勉強初期は法令の勉強に力を入れるべきだし、直前期に一般知識ばっかりやっていたら法令が疎かになってやばいですから。
半年くらい前から徐々にエンジンをかけていって、法令の勉強をメインにしながらも一般知識の知識も積み重ねていくイメージが良いでしょう。
まとめ

いかがでしょうか?
行政書士試験の一般知識の対策法について解説しました。
最後に復習しましょう。
以上のようになります。
行政書士に受かるためには一般知識の攻略は必須。
法令科目を中心に学習しつつも、足切りラインは超えられるように一般知識の勉強も重ねていきましょう!
ではまた!
▼あわせて読みたい記事はこちら▼
行政書士の受験勉強でまとめノートは作らない方が良い理由【音読が有効】


