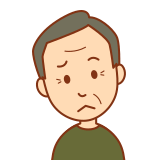
中年になり、行政書士の資格でも取ろうかと思っていますが、将来性について気になっています。実際にどうなの?
このような疑問を持っている方はいませんか?
近年でも行政書士に対して暗い話題をちょくちょく聞きます。
AIで仕事がなくなる、オンライン申請が普及して依頼しなくなるetc
では巷で言われるように行政書士は本当に将来性は皆無なのでしょうか?
この記事では行政書士の将来性がないと言われる3つの理由を解説し、ついでに行政書士業界の未来について個人的な意見を書いていきます。
ぜひ行政書士の将来性を考えるきっかけにしてください!
行政書士の将来性がないと言われる3つの理由

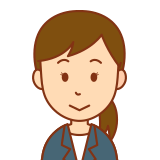
ここからは行政書士の将来性がないと言われる理由を3つ紹介していきます。あなたはどう考えますか?
インターネットの普及で行政書士に依頼しなくても自分でできるようになる
2000年代に入り日本の家庭や会社でも急速にインターネットが普及しました。
その頃からボチボチ言われていたことですが、ネットの普及により行政書士に依頼せずとも各種書類の作成が簡単に出来るようになり、行政書士の仕事はなくなると言われていました。
それまでは書類を作るには知識が必要で、その知識も簡単に得られるようなものではなく、役所に足を運んでも今のようにサービス精神のある対応などしてもらえず、結局はプロの行政書士に頼むということが多かったようです。
ネットが普及すると書類を完成させるための知識がググったら簡単に手に入るようになり、やろうと思えば自分で出来る人が増えていくだろうと言われて、行政書士の将来性を危ぶむ声はこの頃から既にありました。
オンライン申請が普及して手軽に個人が申請できるようになる
ネットで書類の書き方が分かっても、実際に申請するためにはお役所に足を運んでいかないといけません。
それも一度で済めば良いですが、追加書類や補正などで何度も足を運ぶことも珍しくありません。
これから商売をする人がそんな暇はなく、そこで行政書士の出番というわけでした。
しかしネットが普及することが進み、役所でもオンライン申請に対応するようになっていきます。
役所まで行くのは面倒だけど、オンラインでサクッと申請できるのなら自分でやってしまおうかと考える人も出てくるでしょう。
そんな予想から今度こそ行政書士の将来性は無いだろうとオンライン申請の普及を鍵に言われるようにもなりました。
特に近年はマイナンバー制度の影響もありこの考えが顕著です。
AIが普及して申請書類をAIが作ってくれるようになる
そして現代になり、今度は行政書士業界だけでなく至る所でAIの存在が騒がれています。
「AIによって多くの仕事がなくなる」
「AIで士業は全滅する」
確かにAIというのは一部の士業の仕事を人間がやるより圧倒的に高速に正確にこなしてくれるでしょう。
定型的な書類作成もAIの得意分野だと思います。
ではAIによって行政書士の未来は暗く、将来性はなくなったのでしょうか?
僕はそうは思いません。
生き残る行政書士|専門知識を生かしたコンサル業務がカギ
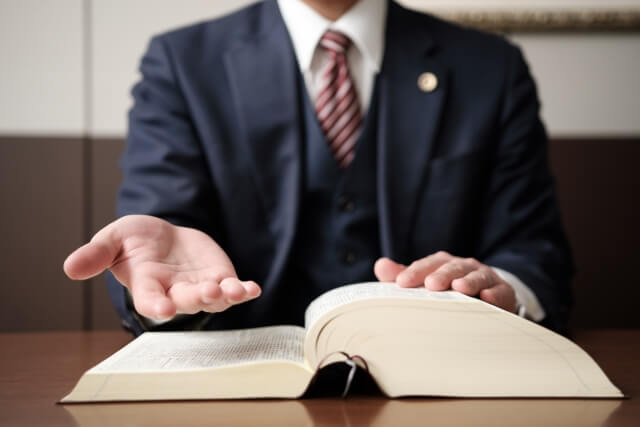
AIは定型的な書類作成は得意分野ですが、苦手なこともあります。
それは相談業務や各種コンサルティング業務だと思います。
- こんな商売がしたいけど、どんな許可がいるのか
- 将来の事業内容を考えたらどんな許認可を取得したら良いか
- 業界の動向を加味しての適切なアドバイス
- 経営者の悩みの相談
AIが普及していっても結局仕事をする人の悩みは尽きないと思います。
そんな時に専門知識を持った、人間的に魅力溢れる人が近くにいれば、経営者も相談して仕事を依頼でもするかとなるのではないでしょうか。
ただの作業ならAIに任せれば良いのですが、答えのない問いを考えたり重要な意志決定をする場合はやはり人間同士の議論が必要だと思います。
そんな時に信頼される国家資格者である行政書士としての地位を築けたら将来性は安泰でしょう。
行政書士の業務範囲は法改正で拡大していく
それに行政書士の仕事がAIで先細りしていくわけでもないと思います。
行政書士の業務範囲は各種法改正によって、どんどん拡大していくものです。
新しい行政手続きが生まれたら、その手続きについては最初はみんな素人なのですから、そこにチャンスはあります。
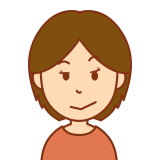
これまでも民泊・ドローンなど新しい行政書士の仕事が法改正によって生まれましたね
新しい分野でいち早く第一人者になって稼いでいる人もいます。
こういった資格の特性を考えると将来性はむしろあるのではないでしょうか?
【将来性あり】行政書士は変化に対応していけば未来は明るい?

これまでも時代の変化によって行政書士はオワコンだとよく言われてきていました。
でもそんな変化の中でも行政書士は今日に至るまで生き残っています。
もちろん時代について行けず廃業したところもあるでしょう。
では生き残ったところと廃業したところの違いは何か?
それは「変化に対応したこと」だと僕は思います。
こういった時代に合わせた働き方をデキる人が行政書士として長く活躍していくのだと思っています。
ダブルライセンスで幅を広げるのも良い
変化に対応していくためには時代を切り開いていく武器が必要。
何を身に付けるかは人それぞれですが、例えば他士業の資格を取って、ダブルライセンスを目指すのも一つの道です。
行政書士と司法書士、将来性はどっちにある?
司法書士に限らず社労士や税理士などの他の士業もそうですけど、行政書士と同じようにネットの浸透やAIの発達によって多かれ少なかれ仕事がなくなっていくこともあるでしょう。
これまでと同じ業務を同じやり方でずっとやっていてはいつか食えなくなる日が来るかもしれないのはどの士業でも同じです。
「どの士業だから安心」というものではなく、将来性があるかないかは結局は資格の使い方次第ではないでしょうか。
例えば司法書士はこれからの超少子高齢社会で、成年後見や相続など活躍する機会はますます増えることかと思います。
では司法書士全員に将来性があるから安心かというとそうではなくて、時代に適応して上手く資格を使った人限定ではないでしょうか。
まとめ

行政書士の将来性について、解説してきました。
もう一度結論を言うと、
行政書士は将来性があります!
ただしそれは「変化する激動の時代に対応できる人」じゃないと行けません。
いつまでも定型的な書類作成を職人のようにやっていては食えなくなるかもしれません。
今までも幾多の困難を行政書士たちは知恵を絞り乗り切ってきました。
そしてAI全盛時代になっても行政書士が社会から求められる価値というのはきっとあるはずです。
▼あわせて読みたい記事はこちら▼




