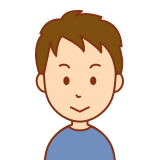
最近行政書士の資格に興味を持ちました。どんな仕事内容なのかイマイチ分からないのですが教えてくれませんか?
こんな疑問を持つ方はいませんか?
この記事では行政書士の仕事内容についてサクッと解説しています。
業務の幅が非常に広い行政書士ですが、ポイントを絞って分かりやすく説明できるようにするので、ぜひ最後まで読んでみてください!
昔は「代書屋」、今は「街の法律家」と呼ばれる行政書士

行政書士の仕事内容を理解するには過去と現在のキャッチコピーを知ることが近道です。
- 過去は「代書屋」
- 現在は「街の法律家」
代書屋とはまさに文字の通りで、他人の代わりに文字や文章を書いて報酬を得る仕事です。
日本は昔から識字率が高くて読み書きできる人はそれなりに多かったわけですが、それでもお役所に出す書類などの専門性の高いものは書けないという人もいました。(昔は今みたいにネットに雛形が落ちてるというわけでもないですからね)
そこで、そういった人たちのために「代書」して商売をする人たちがいて、それが現在の行政書士に繋がっています。
ちなみに現代でも一昔前に自動車学校の周りに行政書士が小さな事務所を建てて、書類の作成代行とかやってたのをご存知でしょうか?
さすがに最近はネットの発達で少なくなりましたが直近までそういう商売も残っていました。
そして現代になり、行政書士は「街の法律家」と呼ばれるようになります。
時代の変化と共に業務内容の幅も広がり、ただ単に「代書」するだけではなくて、コンサルティングをしたり、予防法務に取り組んだりと活躍の場は広がっています。
行政書士の仕事内容は大きく分けて3つに分かれます。
それを次の項目から解説していきます。
▼副業的に行政書士の資格を活用している人もいます▼
【行政書士の仕事内容1】官公署に提出する書類の作成代行

行政書士の仕事内容としてまず挙げられるのが「官公署に提出する書類の作成代行」です。
分かりにくいですよね?(笑)
要はお役所に提出する許認可関係の書類を依頼者に代わって作成・提出しますよということです。
日本では新しく商売をする場合は役所に申請をして許可を得なければいけない場合が多々あります。
飲食業でも建設業でも無許可の人がめちゃくちゃな商売をしてしまったら、お客さんに迷惑がかかるので、許可制にしてちゃんとしている所しか商売できないようにしています。
しかし役所に提出する書類というのは複雑なことが多いです。
初めての申請だと再提出や不備などで何度も役所に足を運ぶ可能性があります。
これからの商売で忙しい人がそんな面倒な事はやってられないということで、お金を払って行政書士に依頼をするのです。
許認可の具体的な業務内容
具体的には以下のような仕事内容で行政書士は活躍しています。
- 建設業許可
- 古物商許可
- 風俗営業許可
- 飲食店営業許可
- 道路使用許可
- ドローン許可
- 自動車登録
- 車庫証明
他にもまだまだたくさんあります。
この中では建設業許可が行政書士市場の中でもかなり大きいですね。
建設業許可は行政書士の大メジャー業務であり、メインにしている人もたくさんいます。
あとは車庫証明などは新人行政書士が第一歩として手掛けているイメージです。
【行政書士の仕事内容2】権利義務、事実証明に関する書類の作成代行
権利義務、事実証明に関する書類の作成も行政書士の仕事です。
これまた「どういうこと?」という声が聞こえてきそうです(笑)
私たちは生活していく上で様々な契約をして、権利を得たり義務を負ったりしています。
個人間のお金の貸し借り、示談、遺産分割協議などなど。
本当にたくさんありますよね。
そういった日々の約束事を書面にしてきちんと残しておかないと、後々言った言わないの水掛け論になる可能性があります。
もしかしたら重大なトラブルに発展する可能性もありますよね。
だからそういった書面を報酬を得て作成できるような仕事が行政書士の仕事内容になるのです。
だって、素人が適当に書いた契約書が穴だらけで契約書として使い物にならなかったら嫌ですよね?
そんな契約書が蔓延したら国民生活が裁判やトラブルだらけの世界になってしまいます。
それを防ぐためにも国家資格者の行政書士の仕事として決めているのです。
権利義務・事実証明の具体的な業務内容
- 示談書
- 契約書
- 遺産分割協議書
- 念書
- 嘆願書
【行政書士の仕事内容3】審査請求・再調査・再審査請求
許認可などを申請して不許可になった時など、どうしても行政庁の決定に納得ができない時があります。
そういう時は審査請求・再調査・再審査請求などの救済制度があり、行政庁に対して不服を申し立てることができます。
国民の権利利益を守るためにはこのような制度も必要ですよね。
そしてこういった制度を使うためには、もちろん行政庁に必要書面を提出するわけですが、その書面の作成ができるというのが行政書士の仕事の3つ目です。
こういった不服申立ての代理や書類作成は「特定行政書士」という法定の研修を受けて考査に合格した行政書士しかできません。
具体的な業務内容
- 出入国管理の不服申立て
- 建設業許可・不許可の不服申立て
- 産廃業許可・不許可の不服申立て
行政書士の仕事内容の特徴を分かりやすく解説
行政書士の仕事は、
- 営業して仕事を獲得して
- お客さんと打ち合わせやヒヤリングをして
- 申請書類を完成させて
- 官公署に申請書類を提出して
- 必要があれば補正をして
- 無事許可が出たら受け取りをして
- お客さんに納品をして報酬を頂いて完了
大まかにこういう流れになります。
一連の流れの中で必要とされる能力としては、
- 営業力(重要!)
- コミュニケーション能力
- ヒヤリング能力
- 事務処理能力
- フットワークの軽さ
など多岐にわたる能力が求められます。
ただ黙々と書類を作るだけではないのですね。
やはり一番大事なのは営業力だと思います。
これがないとそもそも仕事がなくて食えなくて廃業一直線ですからね。
行政書士は国民と行政を繋ぐ橋渡し役
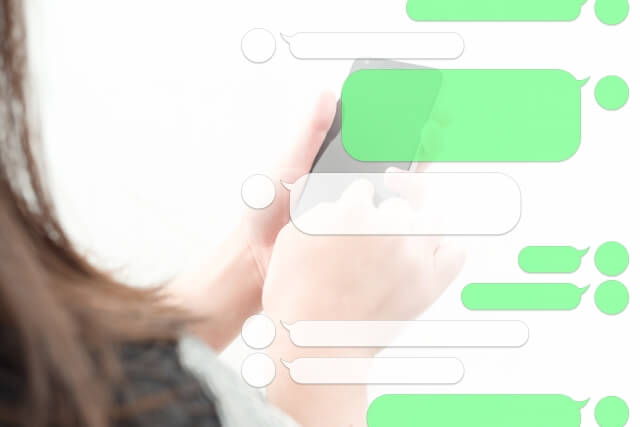
以上のように行政書士の仕事内容は大きく分けて3つの分野があります。
その中でも多くの行政書士が手掛けているメジャーな分野が「許認可」の分野で、行政書士はまさに「許認可申請のプロフェッショナル」と言えます。
許認可のプロである行政書士は国民と行政を繋ぐ橋渡し役として期待されています。
一般の人にとっては人生に何度もあるかないかの手続きのためにたくさん調べ物をして何度も役所に行くなんて効率が悪いです。
また、行政庁の職員にとっても、何度も何度も同じ説明を一からやっていたら仕事がいつまで経っても終わりません。
そこで行政書士の出番というわけです。
国民は時間を節約して本業に集中できる、役人は効率的に申請を捌ける、行政書士は依頼人の役に立ち報酬を得られる。
これが行政書士の仕事の真髄です。
まとめ
いかがでしょうか?
行政書士の仕事内容について解説しました。
このような仕事を通して国民と行政庁を繋ぎ、円滑な社会生活を送る手助けをする仕事なのです。
個人的な感想になりますが、色々なビジネスのお手伝いが出来る行政書士の仕事内容というのは非常に面白いものだと思います。
僕は一つのことに一点集中して取り組むよりたくさんの事をバランス良くやるのが好きで、興味の幅も広いので、行政書士に魅力を感じて取得しました。
そのような方はぜひ取得を検討してみませんか?



