これから行政書士試験を受けようという人は問題を解く順番や時間配分について考えたことはあるでしょうか?
行政書士の問題には択一式や多肢選択式、記述式など多様な種類があり、180分という限られた時間の中で最大限の得点を挙げられるように意識して解いていく必要があります。
そのためには問題の解く順番にも注意するし、各問題にどれくらい時間をかけるのかという時間配分にも気を付けないといけません。
この記事では行政書士本試験における上記のような注意点を解説していきます。
これから行政書士試験を受けようという人には参考になる内容だと思うので良ければ最後までご覧ください。
行政書士試験は基本的に時間が足りない
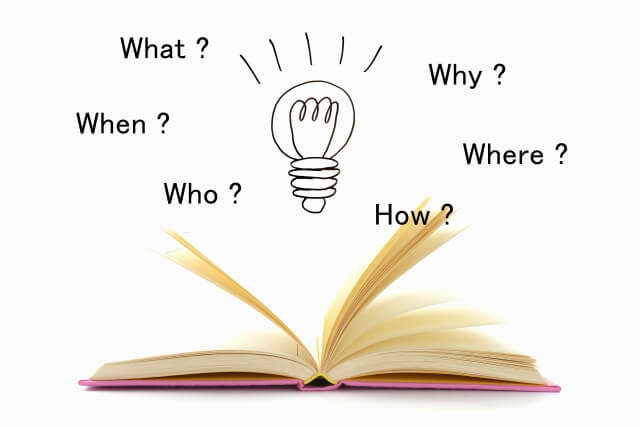
行政書士試験は全60問、50ページ以上に及ぶ問題をたった180分で解いていくという試験で、ある意味時間との戦いでもあります。
特に初めて受験する人は、あっという間に時間が過ぎていって、「もうこんな時間!?やばい、時間が足りない!」という状況になる可能性が高いです。
僕も初めて受験した時は時間配分をミスって記述式や文章理解の問題にかける時間が少なくなってしまい、焦りながら急いで書いた記憶があります。
全部解答を書き終えたのが試験終了時間の1~2分前という非常にハラハラする結果になりました(笑)
特に最初の方は試験会場の雰囲気に飲まれていつもより頭が回転せずに、各問題にかける時間が多くなってしまったことが反省点です。
これから受験する人は、基本的に時間が足りないものと思って、なるべく早く問題を捌いていくことをおすすめします。
かといって焦ってミスしては元も子もないのでそこらへんのバランス感覚が難しいところです。
解く順番や時間配分に注意すると最大限の得点を狙える
僕は問題を最初から順番に解くことを基本にしていましたが、今思えばそれは失敗だったと思います。
解く順番や時間配分のペースを事前に決めておいてそれに従って問題を解く方が最大限の得点を狙えるのではないでしょうか。
次の項目からは自分自身の反省点も踏まえて問題を解くおすすめの順番や時間配分を説明していきます。
とはいえベストな順番は人によって異なるので、あくまで参考程度でお願いします。
行政書士本試験の問題を解く順番は?
問題を解く順番で大事なのは以下のような点です。
- 自信のある問題から解く
- 早く解ける問題から解く
- 時間のかかる問題は終盤に残さない
- 自信のないものや悪問奇問は最後に回す
試験が開始して、早々に全く分からない問題が連続すると動揺してその後の試験にも引きずってしまうかもしれません。
序盤は得意な問題をサクサクやって、エンジンを暖めていきましょう。
そして脳がフル回転する中盤あたりで時間のかかる記述式や文章理解を終わらせます。
終盤では自信のない問題を解いていって分からなくても気にしないようにしましょう。
序盤は行政法か民法の択一式を解いていく
いきなり1問目の基礎法学からやるのはおすすめしません。
基礎法学は聞いたこと無いような問題も多く、初っ端から分からないと結構ショックを受ける人もいます。
だから基礎法学は後回しにしてまずは行政法か民法のどちらか得意な方の択一式から解きましょう。
もしくは基礎法学は間違えても気にしないと最初から思って解くようにするのも良いでしょう。
ウオーミングアップとしては最適だと思うので、段々エンジンをかけていって素早く「行政書士脳」に持っていきましょう。
時間のかかる文章理解、記述式あたりは中盤で攻略する
記述式問題や文章理解問題は解くのにどうしても時間がかかり、試験終盤に残しておくと意外と焦ってミスが出るかもしれません。
だから択一式をそこそこ終わらせて一番脳が回転している状態の中盤付近で一気に終わらせてしまうのがおすすめです。
他にも多肢選択肢や一般知識問題などもあまり後に残しておきたくないのなら早めにやってしまいましょう。
基礎法学、会社法、憲法あたりは終盤でいい
基礎法学は何が出るか分からないし、会社法はそこまで時間をかけて勉強している人も少ないと思います。
そういった問題は終盤に解いて仮に分からなくてもショックを受けないようにしておきましょう。
憲法の問題は序盤、中盤に解いても良いのでそこは好きなタイミングでやりましょう。
行政書士試験の時間配分は?

時間配分として各問題にどれくらい時間をかけるのかは事前にある程度決めておきましょう。
大事なのは「分からない問題はサクサク飛ばして分かる問題をドンドン解く」ということ。
分からない問題を延々と考えて時間がなくなり、分かる問題さえ落とすのが最悪のパターンです。
- 記述式には◯◯分かけよう
- 文章理解は◯◯分を目標に解こう
- 択一式は1問◯分を目標にしよう
普段から問題を解く時間は意識して、本試験でもちょくちょく時計を見て時間配分を確認しておきましょう。
行政書士初受験の人は注意!会場の雰囲気に飲まれるな!

初受験の時は自分でも驚くくらい緊張していました。
シーンとした教室で周りはみんな使い古した参考書を開いていて、頭の良さそうな人ばかり。
試験問題をいつも通り読んでいるはずなのに何故か頭に入らない。
普段の倍くらいかかって1問を解いていく始末。
ようやくいつもの調子が戻ってきたのは試験時間が半分を過ぎたくらいからでした。
そこから巻き返したのですが、最後は記述式にかける時間が足りなくて終了1~2分前になんとか殴り書きを終えるという(笑)
これから受ける皆さんは緊張するなというのは無理かもしれませんが、出来るだけ平常心で受けるように注意です。
後から合格発表を見たら頭の良さそうに見えた周りの人もほとんど受かってなかったですから。
周りのことは気にせず目の前の問題に集中です。
まとめ
行政書士の本試験の問題を解く順番と時間配分について書きました。
これから行政書士試験を受ける人は参考にしていただけると幸いです。
もちろんベストな順番は人それぞれですから、自分なりに考えて試行錯誤してアップデートしていってください。
最後に復習しておくと、
- 得意な問題・サクサク解ける問題から解く
- 民法・行政法の択一式から解くのがおすすめ
- 基礎法学や会社法などは終盤に
- 時間のかかる記述式や文章理解は調子の出てきた中盤で
- 事前に各問題にかける時間配分を頭に入れておく
では!
▼あわせて読みたい記事はこちら▼


